 |

-炎柱・煉獄杏寿郎-
|
|
|
***ネタバレ知りたくない方はご注意ください***
|
|
|
煉獄杏寿郎(れんごくきょうじゅろう)鬼殺隊を支える最上級隊士である“柱”の一人。「炎柱」の称号を持つ。
正義感が強く、明朗快活で豪快な性格。決して揺らぐ事のない信念は、力強さと意志の強さを感じさせる。
剣士としての実力は言うに及ばず、咄嗟の戦況把握能力と、その場に居合わせた若輩の剣士達の実力を瞬時に見抜いた上で、それぞれに的確な指示を飛ばす戦術眼も持っており、指揮官としても非常に優秀である。
|
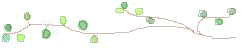 |
その戦闘能力は非常に高く、剣技においては天賦の才を弛まぬ修練と最前線で戦い続けた経験で磨き抜いており、鬼殺隊最上位陣である柱達からも絶対的な信頼と共に一目置かれていた。
無惨の血で強化された上で 200人の乗客を人質にしていた"下弦の壱"の魘夢をその上で圧倒して抑え、連戦での"上弦の参"である猗窩座も、その実力を稀に見る好敵手として絶賛している程である。さらに階級「甲」の頃に当時の"下弦の弐"を単騎で撃破して柱に登りつめている。柱の中でも腕力、機動力共に非常に安定して高い事が分かる。 |

|
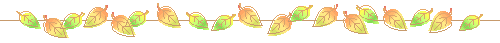
-無 限 列 車 編- |
|
**前 夜**
事は柱合会議後、間をおいてから下った炎柱煉獄杏寿郎への出撃命令に端を発した。

無限列車において40数名の乗客が行方不明になるという事件が勃発し、派遣された鬼殺隊員も消息を絶っていた。事態を重く見た鬼殺隊は杏寿郎の派遣を決定した。
→ 
|
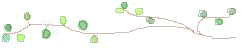 |
駅の改札口でふくとトミから大量の弁当を購入し、昨晩の事の礼を言われた杏寿郎は、父に二人の事を伝えると約束し、改札を通過した。

炭治郎、善逸、伊之助も乗り込み、無限列車は出発した。
「美味い!!」を連呼しながら食事している所に炭治郎、善逸、伊之助と合流し、彼らと顔合わせを行った。
同席した炭治郎から鴉を通して合流指示が出された事を知り、同時に彼からヒノカミ神楽について問われるが「知らん」と即答し、愕然とさせた。
一方、興奮して騒々しい伊之助と彼に手を焼く 善逸に対し、「危険だぞ、いつ鬼が出て来るか判らないんだ」と、たしなめた。そして任務の概要を大まかに説明した。
そこに車掌が切符の確認にやってきて切込みを入れ、魘夢の術が発動、魘夢配下も行動を開始した。 |
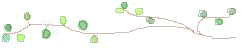 |
眠らされた杏寿郎は父に柱になった事を報告した日の夢を見ていた。その報告を受けた父の態度に反発も失望もせず、気丈に弟を励ましていた。
その夢の中に潜入した三つ編みの少女はその無意識領域で杏寿郎の精神の核を破壊しようとしたが、実体の方で阻止された。本来なら術がかかってる状態では動けない筈だったのだが、杏寿郎は敵の予想の範疇を超えた生存本能を持っていたのだった。

ここでは割愛するが、魘夢配下の目論見は全て失敗し、元々術にかかっていなかった禰豆子の助けでいち早く目覚めた炭治郎が鬼を倒すべく動き出した。
しかし、すでに魘夢はすでに自身の体を列車に融合させており、鬼殺隊士達の廃人化が失敗した為に彼らを疲弊させて倒す作戦に切り替えた。禰豆子の助けで覚醒した伊之助、覚醒してなくとも動ける善逸も行動を開始したが、客車内に触手を浸潤させて挑発してくる魘夢に炭治郎達は全く連携が取れず、近場の客たちを守るだけで精一杯だった。
|
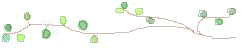 |
そこに最後に自力で覚醒した杏寿郎が強烈な斬撃を加えた。
「うーん…、うたた寝してる間に、こんな事態になっていようとは…。よもやよもやだ、柱として不甲斐なし。穴があったら入りたい!!」
この台詞と共に二太刀目の斬撃を加え、かまぼこ隊に合流して指示を出した。
双方根競べで、鬼の頸が斬られるか、鬼殺隊が疲弊して倒されるかだった。この場を凌ぎきったのは鬼殺隊の方で、伊之助と炭治郎が頸の切断に成功した。
魘夢の断末魔に列車は激しく脱線したが、杏寿郎が繰り出した技によって衝撃が緩和され、夥しい死者が出てもおかしくない規模の脱線を死者ゼロで乗り切った。 |
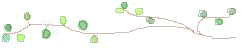 |
 しかし、魘夢撃破後に突如強襲してきた猗窩座と一騎討ちとなり、互角の勝負を展開するが、鬼の不死性と超再生力が歴然たる差となり徐々に追い込まれ、ついに鳩尾を貫通する致命傷を受けてしまう。 しかし、魘夢撃破後に突如強襲してきた猗窩座と一騎討ちとなり、互角の勝負を展開するが、鬼の不死性と超再生力が歴然たる差となり徐々に追い込まれ、ついに鳩尾を貫通する致命傷を受けてしまう。
絶命が決定的となった状況で、杏寿郎の戦士としての強さや練度をいたく気に入った猗窩座から幾度も、鬼となる事での延命を誘われるが、限りある生命の輝きを語り、この再三の勧誘を断固拒否。
最期の力を振り絞って、鬼の致命的弱点である日光が現れる夜明けまで猗窩座を拘束するという形での相打ちを試みるも、後一歩のところで逃走を許してしまう。
|
 |
しかし、未だ輝きが十全に足らぬ日輪を守り抜けた事に希望を見出し、少年達に鬼殺隊士としての心得を説いた後、陽光に照らされながら逝った。
→ 
|
| 無限列車編は【原作では――】7巻54話『こんばんは煉獄さん』~8巻66話『黎明に散る』となります。 |
|
**【原作】7巻第53話『君は』については、アニメ『立志編-最終話』の内容になっていますので一連の流れで読みたい方は、こちらから一読されるのがお薦めです。
**【原作】67話『さがしもの』/68話『使い手』/69話『前へ進もう少しずつでも構わないから』は無限列車での戦闘後、炭治郎が炎柱の煉獄杏寿郎の最後の言葉を伝えに煉獄家へ赴く話になります。
**【原作】8巻70話『人攫い』は、次なるアニメ『遊郭編』への序章となっています。
|

|
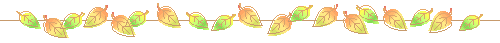
-煉獄杏寿郎の過去-
|
|
代々“炎の呼吸”を伝え継いできた剣士の名門・煉獄家の長男として生を享け、元柱の父を持ち、幼少から修練に励んできた生粋の鬼殺隊士。幼い頃に故人となった母親から説かれた言葉と、抱きしめられた腕の温もりを心の支柱としている。
少年時代は父から情熱的な指導を受けていたが、母の死と同時期に父が酒に溺れ指導と育児を放棄した為に、以降は一人で家にあった僅か3巻の炎の呼吸の指南書を読み込む事で、殆ど独学で炎の呼吸を習得し、柱にまで登りつめた。
父に背を向けられて心無い言葉を返される事に寂しさや苦しみも抱えていたが、己の責務を果たす為に年の離れた弟を励ましながら前を向き続けた。柱合会議さえ蔑ろにするようになった父の代理で参席するなど、表向きも煉獄家を切り盛りしていた模様。
|

|
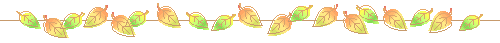
―下弦の鬼を倒し、柱となる― |
|
炭治郎が鬼殺隊の剣士となる少し前。弟子として引き取った甘露寺蜜璃がわずか半年の修行で最終選別を突破し、煉獄は弟の千寿郎と共にその快挙を喜んでいた。
そこに柱合会議が開かれるという連絡が届くも、父であり当時の炎柱である槇寿郎は「どうでもいい」と言い放って出席を拒否。妻である瑠火の死の前後から槇寿郎は覇気を失い、ここ数年は鬼を切る任務にも酒を持ち込むようになり、すっかり堕落してしまっていた。そのため、柱合会議には代わりに煉獄が出向くこととなる。 |
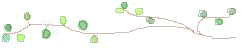 |
柱でもない煉獄が柱合会議に出席することに、当時の柱たちは懐疑的な目を向ける。特に風柱である不死川実弥は不愉快な様子を隠そうともせず、いずれ自分も柱になると豪語する煉獄に「柱はそう甘いものじゃない」と言って殴り掛かる。その攻撃を受け止め、それが彼なりの激励であることを察して礼を言う煉獄。
そんな煉獄に、鬼殺隊のトップである御館様こと産屋敷は、「柱になるというのなら、それに足る力があることを自分自身で証明しなければならない」と告げ、彼にとある任務を申し渡す。
鬼の中でも別格の力を持つ十二鬼月。その下弦の一人だと思われる鬼が、最近帝都に出没している。それを討伐してこいというのだ。煉獄は産屋敷から提示された任務を快諾し、甘露寺や他の隊士と共に帝都へと赴く。 |
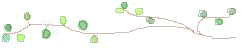 |
帝都に到着し、潜伏している鬼を探し出そうとした矢先、煉獄たちは銃と爆弾による攻撃を受ける。煉獄が向かった先にいたのは果たして、十二鬼月が一人、下弦の弐に位置する軍服姿の鬼だった。
 佩狼(はいろう)という名のその鬼は、「今こそ復讐の時」と宣言して煉獄に襲い掛かる。影を自在に操る血鬼術を駆使し、そこから無数の銃器や爆弾を取り出して攻め立ててくる佩狼に煉獄は苦戦するも、なぜ相手が自分に復讐を誓っているのかどうしても分からずにいた。間違いなく初対面のはずなのだ。 佩狼(はいろう)という名のその鬼は、「今こそ復讐の時」と宣言して煉獄に襲い掛かる。影を自在に操る血鬼術を駆使し、そこから無数の銃器や爆弾を取り出して攻め立ててくる佩狼に煉獄は苦戦するも、なぜ相手が自分に復讐を誓っているのかどうしても分からずにいた。間違いなく初対面のはずなのだ。
佩狼が影から作り出した狼の群れと、街中に仕掛けられた爆弾への対処を甘露寺たちに命じると、煉獄は単身佩狼との戦闘を開始する。沼のように刃を飲み込む影の狼に苦戦しながらも甘露寺たちは役目を果たし、佩狼は「このままでは他の剣士が戻って来て総攻撃される」と焦り始める。
さらにそのタイミングで、佩狼は煉獄一人を仕留めることもできずに用意していた銃弾と爆弾を使い切ってしまうのだった。 |
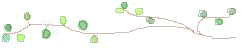 |
佩狼はかつて、炎のような色の髪をした鬼殺隊の剣士に殺されかかったことがあった。酒徳利を片手に、まるで覇気を感じさせなかったその剣士からなんとか生き延び、恐怖と屈辱を怒りに変えて十二鬼月にまで上り詰めた。
しかし目の前にいる剣士は、あの時の剣士と同じ髪の色をしてはいるが、別人のような覇気を放っている。「本当にあの時の剣士なのか」との迷いを振り払い、なお煉獄を殺すべく、佩狼は何か武器は収納していないかと自身の陰の中を探す。
そこから転がり出した一本の刀を見て、佩狼の脳裏に人間だったころの記憶が蘇る。彼はかつて、浅葱の着物を来て国のために刀を振るうも、銃器を持った新しい軍隊の前に敗れて命を落としたのだった。 |
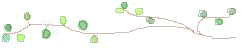 |
生前の記憶と誇りを若干ながらも取り戻したのか、佩狼は一人の武士として煉獄に勝負を挑む。煉獄もそれに応え、“炎の呼吸”の奥義“煉獄”で迎え撃つ。両者の激突は煉獄に軍配が上がり、佩狼は「いい太刀筋だ」と勝者を称賛しながら滅びる。
十二鬼月を倒したことで、煉獄は槇寿郎の跡を継ぎ、炎柱となる。「弱き人々のために力を尽くす」という今は亡き母との約束を胸に、煉獄はその肩書きにふさわしい力量と溌剌とした快男児っぷりを発揮しながら、柱として活躍していくのだった。
|
|
|